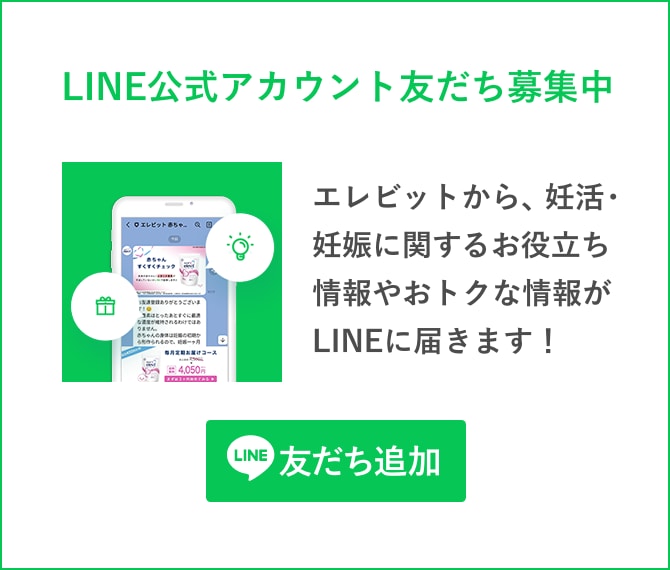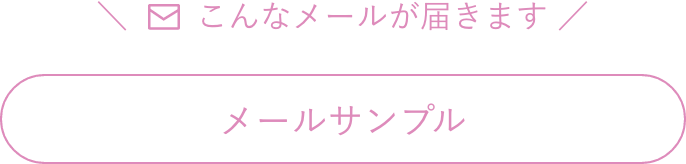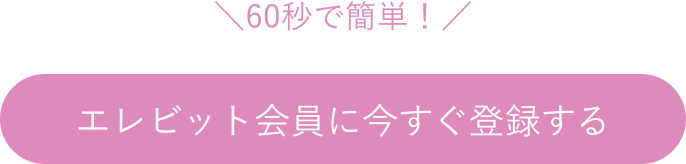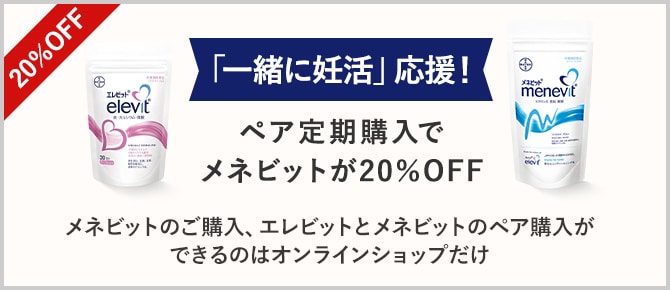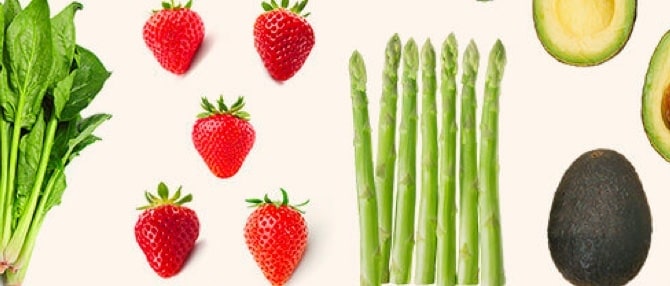トップ> エレビットpresents 大切なあなた>第1回 ダイアモンド☆ユカイさんと、キンタロー。さん 〜スペシャルインタビュー:順天堂大学医学部教授の牧野真太郎さん〜
子どもがほしいと思ったきっかけ、男性不妊の体験談を伺いました
第1回 2021/11/07放送
ダイアモンド☆ユカイさんと、キンタロー。さん
〜スペシャルインタビュー:順天堂大学医学部教授の牧野真太郎さん〜
中村:今回のゲストはダイアモンド ユカイさんとキンタロー。さんです。
ダイアモンド ユカイさんというと、双子のパパであり、年子のパパで、私の中の育児の大変度合いの第1位は年子育児、次に双子育児で、このトップ2を兼ね備えられていると思います。
ダイ:僕じゃなくて妻が大変ですね。
大変という言葉はもう普通になってきました。逆に楽しいですよね。
中村:にぎやかでしょうね。
そしてキンタロー。さんは、なんと今おなかにお2人目がいらっしゃいますね。おめでとうございます。見た目でもわかるくらい大きいですけれども、出産のご予定は?
キン:ありがとうございます。出産予定は、年末を予定しています。2人目は1人目で1回通ってきた道を通るので、「心に余裕が生まれるのかな」と思ったんだけど、意外や意外。同じように心配、心配ですね。
体外受精で生まれた子どもの割合は約16.1人に1人
中村:子どもを持つこと、子どもを授かる形には、多様性があります。
例えば、日本産科婦人科学会の調査によると、2018年に体外受精で生まれた子どもの数は、1年で56,979人。その年に生まれた子どもの、約16.1人に1人の割合です。この数字をおふたりはどう見ますか?
ダイ:普通にすれ違う人が体外受精で生まれた子どもだったりするってことだからね。だからもっともっと、みんなでオープンに情報交換してもいいよね。
キン:思っていたより多いと思いました。昔だったら授かれなくて悩んでいたご夫婦が、今の時代、授かれるようになったのは医療の進歩によってそうなっているんだな、と思います。この流れでどんどん認知度も広がって、助成金など支援の面でも良くなっていってほしいなと思いますね。
中村:クラスでひとりふたりは当たり前の時代になってきましたが、不妊治療に関しては、まだまだクローズな印象がありますよね。
子どもがほしいと思ったきっかけ
中村:おふたりは体外受精でお子さんを授かった経験をお持ちです。
そこで父親と母親、それぞれの立場からお話を伺いたいと思っています。まずは、おふたりが、「子どもがほしいなあ」と思ったきっかけをお話していただけますか?
ダイ:アメリカのファミリーみたいなのがあこがれでね。子どもは自然に授かるものだと思ってた。
40歳過ぎて一度、離婚を経験しましてね、ファミリーを持つ結婚をしたいと思って再婚した時、妻も実は30歳過ぎてて。
妻が妊娠するのに自分の身体が心配だから、どんな状態なのか調べてみたいって言うんで、付き合いで近くのクリニックに行ったんですよ。クリニックは満員だったんだけど男性がいなかったね、俺しか。
そこで「あなた調べてみませんか」って言われて。「なんで俺が調べるんだよ」と思ったけど検査したよ。
中村:でも当時、男性がチェックするみたいな話もなかったですよね。女性がまず先に検査するという感じでした。
キン:私は、家族というものにもともと強い思い入れがありました。私は両親を20代で亡くしたんですが、自分が育ってきた家族が幸せの象徴で。
両親を失って絶望を感じたときに、「いつか自分も家族を持ちたい」っていう気持ちを糧にしてきたので、結婚も、子どもを授かるのも幸せな家庭を目標としていました。なので、最初から「絶対子どもがほしい!」っていう気持ちが強かったです。
中村:すぐにクリニックに通われたんですか?
キン:それが、結婚したと同時に長期戦の仕事が舞い込んできて、結婚したあとしばらく妊活自体ができなかったんです。でも、自分がもう30歳半ばすぎていたので、焦りもあって自分だけ検査を先に受けたら健康だったので安心してたんですね。そこから仕事が落ち着いて、さぁ妊活ってなったときに、何回かタイミング法でトライしたんですけど授かれなくて「あれ?」っていうところから始まりました。
中村:キンタロー。さんの旦那さんはどうやって検査を受けてくれたんですか?
キン:うちの旦那さんは病院に行くのをめんどくさがっていて。そこで旦那さんの検体を採取してもらい、自分で病院に持って行きました。
ダイ:正直言って恥ずかしいんだよね。男性はこういうところで繊細になっちゃう。女々しいというか。
中村:男性の不妊検査ついて、産婦人科の先生にインタビューをさせていただきました。一緒に見てみましょう。

妊活する上で取り組んだこと
中村:さて、妊活を考えたときに、おふたりもクリニックに通われたとおっしゃっていました。そこからご自身で妊活のために取り組んだことはありましたか?
キン:妊娠にいいとされるものはけっこうトライしました。たとえば葉酸サプリメントを飲んだり、ダイエットしてみたり。
ダイ:俺はないね。子どもを授かってから、健康オタクロッカーになったんだけど、それまでは暴飲暴食。好き勝手にしてたかな。
中村:この差って、けっこう女性と男性で大きいと思いませんか?
ケンカの要因になりますよね。女性がこれだけ整えているのに、なんでパートナーである男性は整えてくれないのかと。
男性不妊とわかったとき
ダイ:妻と一緒にクリニックに行ったスタート地点では知識がなかったの。「付き合ってやる」っていう、上から目線だった。
ところが男性不妊だったわけよ。無精子症。
「精子ゼロです」って言われて、もう一回検査したのよ。今度こそって思ったんだけど、やっぱりゼロだったんだよね。そこから覚えてないね。顔面蒼白で落ち込んだ。
妻とお台場の海が見えるレストランに行ってさ、そこで、「俺じゃないほうがいいんじゃないの?君は健康体だし、パートナーを変えればファミリーを持てるし」って言ったんだよね。そしたら妻に「ユカイさんは子どもみたいなところありますから、ユカイさんを子どもだと思ってこれからもやっていきましょう」って言われて。それでも、「何がわかるんだよ」って、そのくらいひねくれちゃってさ。
中村:そういった言葉をかけてくれた奥様に対しても、「お前にはわからないじゃないか」と言うほど、まさかの出来事だったということですよね。
ダイ:そうだね。人生が187度くらい変わっちゃったね。今までの生き方はなんだったんだろうっていうぐらい、壁にぶつかって吹っ飛ばされちゃったの。そんな感じだった。
中村:キンタロー。さんの旦那さまはいかがでしたか?
キン:うちも同じ無精子症だということで、私も頭が真っ白になっちゃって、ネットで無精子症って調べたら、ダイアモンド ユカイさんの体験談がでてきて。芸能人の方が体験談を発表してくれるっていうのが、すごく励みになったというか、「私たちだけじゃない」って救われたんです。
ダイ:よかった。「こういう人でも授かることができるんだ」って感じてもらえると思ってね。
今、仕事で活躍してる女性は、大学卒業して、会社に入って、仕事ができるようになってきて、そうすると30歳くらいになっちゃうんだよ。そのあと妊活をはじめて、もしパートナーが俺みたいな無精子症だったら何にも知らずに、忙しいままあっという間に時間が経ってしまう。これはいろんな人に知ってもらわないとな、ってずっと思ってたの。男性不妊って、あまり認知が広がってないんだよな。
中村:言葉はかなり広がってきたけれど、実際に男性のマインドを変えているかというと、そこはまだこれからという感じですね。
「赤ちゃんへ最初の贈り物」、あなたは何をプレゼントしますか?
中村:おふたりにもうちょっとご夫婦のお話とか、どうやって妊活を乗り越えたのかお伺いしたいんですけれども、一回目はここまでです。
最後にダイアモンド ユカイさんに質問させていただきます。「赤ちゃんへ最初の贈り物」、あなたは何をプレゼントしますか?
ダイ:バラ色の人生(La Vie En Ros)っていう歌を歌いました。でも長女は、全然覚えていない。
全員:(笑い)
中村:今回は深いお話、ありがとうございました。お二人には来週もご登場いただいて、引き続きお話を伺います。
※ラジオ番組「エレビット presents 大切なあなた」をもとにwebコンテンツとして再構成しています。

人生最初の1000日
The first 1000 days
妊娠前からカップルで十分な栄養を摂ることで、
ふたりの間に生まれる赤ちゃんがより良い
「人生最初の1000日」を迎えることができます

※2025年1月 株式会社RJCリサーチ調べ インターネット調査 調査対象:産婦人科、産科、婦人科、生殖医療関連診療科 150名
Last Updated : 2021/Nov/24 | CH-20211124-19