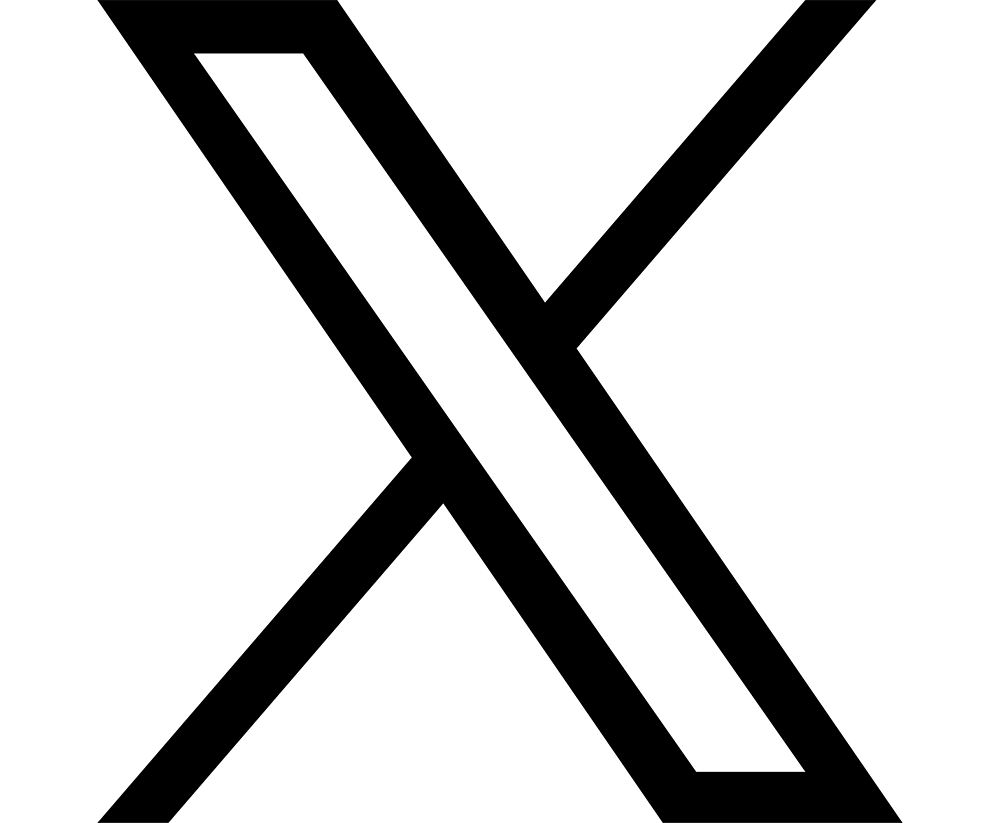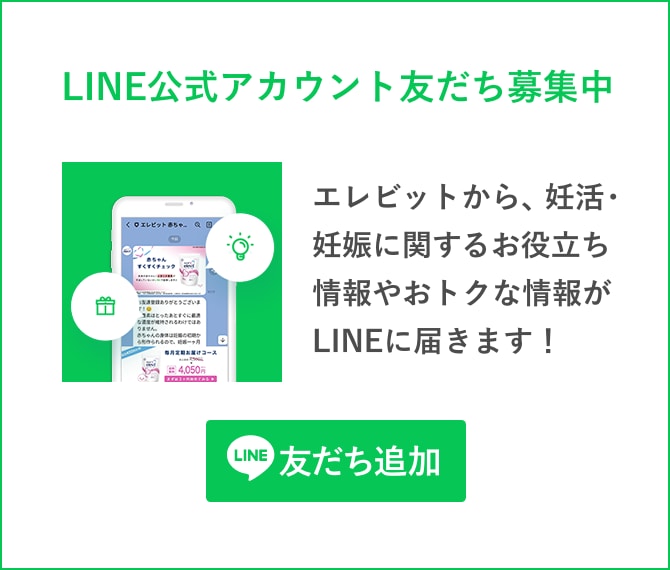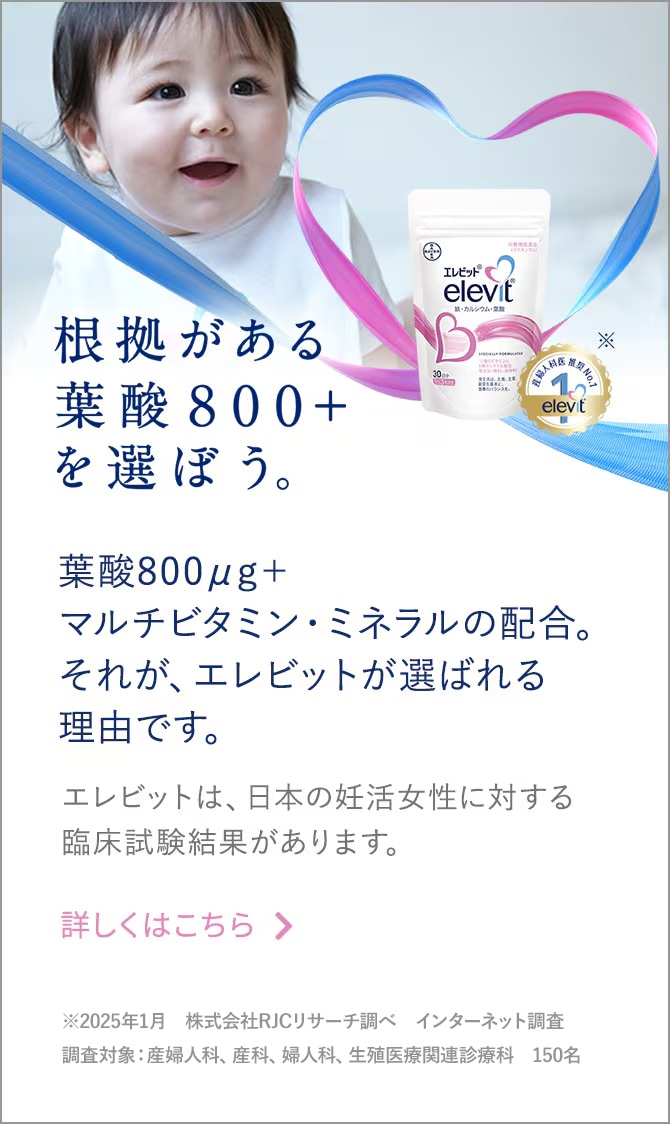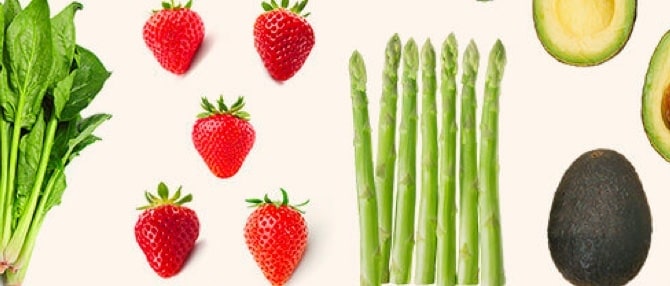トップ>妊娠TOP>妊娠中に知っておきたいこと>妊婦さんの「食事」に関するコラム>妊婦さんにおすすめの食事メニュー。NGな食事も知っておこう!
妊婦さんにおすすめの食事メニュー。NGな食事も知っておこう!
妊娠中の食事は、母体だけでなく胎児にも影響するため、食事メニューには気を使いたいところです。妊婦さんにおすすめの食事と、NGな食事について、詳しく解説します。
妊婦さんの食事が大切な理由
妊娠中は、栄養バランスの整った食事が欠かせません。お母さんが食べた食事が、胎児のからだを作り、妊娠期間の40週の間に胎児の体重は約3kgに成長します。また、出産や産後の育児に向けて、お母さん自身のパワーを蓄えるためにも必要です。
しかし、食べ物によっては、胎児に悪影響を与えるものがあります。
そのため、妊娠中の食事メニューには注意が必要になります。
妊娠中におすすめの食事
妊娠中は、栄養バランスの取れた食事を3食きちんととることが大切です。そして、葉酸、鉄分、カルシウム、食物繊維などの栄養素を意識してとるようにしましょう。
例えば、食事メニューとしては、下記がおすすめです。
「海鮮ニラチヂミ」のレシピはこちら
葉酸と鉄分を多く含むメニューです。これだけで1食が完成します。
「ブロッコリーと卵のグラタン」のレシピはこちら
葉酸とカルシウムの補給にぴったりなメニューです。野菜スープを付ければビタミンや食物繊維も多くとれます。
「鮭ときのこの生姜和風鍋」のレシピはこちら
葉酸の吸収を助けるビタミンB12が多く含まれる鮭と、カルシウムの吸収を助けるビタミンDや食物繊維を多く含むきのこ、そしてからだを温める効果のあるしょうがが入ったヘルシー鍋メニューです。
妊娠中に控え目にしたい食事
母体や胎児への影響が心配されるのが、カフェインやマグロや深海魚などの魚、レバーです。これらの食品は、下記のように胎児に悪影響を及ぼす可能性があるため、摂取は控えたほうが安心です。
カフェインを多く含む飲料
カフェインの摂りすぎは、流産や、赤ちゃんが低体重になるおそれがあります。コーヒーは1日2杯程度までにしておくのがいいでしょう。
カフェインレスのコーヒーも販売されていますので、新たな味の発掘をしてみるのもいいですね。
マグロや深海魚を使った料理
マグロやクジラなどの大型の魚や、キンメダイなどの深海魚は、メチル水銀という物質を多く含む魚です。高濃度のメチル水銀は胎児の脳に影響を与え、神経障害や発達障害を引き起こす可能性があるため、食べる量や頻度には注意が必要です。アジやイワシ、カツオ、タイなどの魚を選ぶようにしましょう。
レバー料理
レバーは、レチノールという動物性ビタミンAを多く含みます。レチノールを摂りすぎると、胎児に先天性の異常などの影響を及ぼす可能性があります。特に妊娠3ヶ月以内の妊婦さんは、鶏レバーや豚レバー、牛レバーなどは控え目にしましょう。
妊娠中にNGな食事
少量でも母体や胎児に悪影響を及ぼす可能性のある食事があります。下記のような食品は避けましょう。
お酒
妊娠中にお酒を飲むと、胎児に奇形や脳障害を引き起こす「胎児性アルコール症候群」を発症する可能性があります。妊娠中は必ず禁酒しましょう。
生肉
生肉には、トキソプラズマという寄生虫やカンピロバクター、腸管出血性大腸菌などの病原菌が潜んでいるおそれがあります。生焼けの肉や生の状態の肉を食べると、胎児の異常を引き起こす場合があります。お肉は中までよく焼いて食べましょう。
生魚
生魚には、腸炎ビブリオやノロウイルスなどの食中毒菌やウイルスがいる場合があります。これらは下痢や腹痛、嘔吐などの症状を引き起こし、子宮収縮や脱水を起こすおそれがあります。
また、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にはアニサキスという寄生虫がいる場合があり、注意が必要です。アニサキスは、激しい腹痛や吐き気、嘔吐などの症状を引き起こします。
中まで火を通すことで、食中毒やアニサキスは死滅しますので、しっかり焼きましょう。
生卵
卵の殻や卵の中には、サルモネラ菌という細菌がいる場合があります。生で食べることで感染する場合があり、腹痛や、激しい下痢、嘔吐などを引き起こし、子宮収縮や脱水を起こす可能性があります。
卵かけご飯は控え、炒り卵丼にすると安心です。
ナチュラルチーズ、生ハム、スモークサーモンなど
ナチュラルチーズなどにはリステリア菌や、トキソプラズマという寄生虫が潜んでいる場合があり、妊婦が感染すると、流産や早産、死産の原因となる場合があります。
積極的にとりたい栄養素は?
妊娠中は、母体の健康や胎児の成長をサポートするために、積極的に摂取したいいくつかの栄養素があります。つづいて、妊娠中はとくに取り入れたい栄養素を紹介しますので、妊娠中の食事内容を考える際の参考にしてください。
葉酸
葉酸は水溶性ビタミンであるビタミンB群のひとつで、細胞の増殖を助ける働きや、新たに赤血球を作り出す役割を持っています。
胎児の成長に欠かせない葉酸は、妊婦の方にとってとくに重要な栄養素です。
数多くの研究で、妊娠する前から葉酸サプリを十分に摂取することで、生まれてくる赤ちゃんの先天異常が起こるリスクを減らせることが報告されています。
鉄分
妊娠中は母体だけでなく胎児にも栄養を送る必要があるため、全身の血液量が普段よりも増えます。日頃貧血気味ではない女性でも、貧血になる可能性が高まるため、鉄分を積極的に摂取しましょう。
妊娠中に鉄分が多く不足することにより、動悸・頭痛・目まい・立ちくらみといった症状が現れることもあります。
カルシウム
乳製品や大豆製品に多く含まれるカルシウムは、そもそも日本人が摂取不足になりがちな栄養素といわれています。妊娠中は胎児の骨格作りに必要不可欠ですが、出産後は母体の骨からカルシウムが溶け出し、母乳中に移行して赤ちゃんに届くため、産後の骨粗しょう症にならないためにも妊娠中からしっかりと体に蓄えておくようにしましょう。
摂取する際にビタミンDを一緒に取り入れることで、カルシウムの吸収がサポートされるため、バランスのいい食事を意識することも大切です。
ビタミンB群
先ほど挙げた葉酸もビタミンB群に含まれる栄養素ですが、ビタミンB2、B6、B12などのビタミンB群は、それぞれ葉酸と深く関わっており、体内での代謝が円滑に行うためには欠かせない成分です。
糖質、脂質、たんぱく質だけを積極的に摂取したとしても、ビタミンB群が足りていなければ代謝がうまくいかず、効率的に活用できません。なかでもビタミンB12は、赤血球に含まれる「ヘモグロビン」の合成に大きく関わっている成分で、不足すると貧血を起こす場合があるため積極的に取り入れましょう。
ビタミンC
抗酸化物質としての役割を担うビタミンCには、鉄分の吸収を助ける働きもあります。
とくに野菜類に含まれる非ヘム鉄はそのままでは吸収されにくく、ビタミンCが吸収しやすい形に変える助けをするため、一緒に摂取することが望ましいです。ビタミンCが不足すると、倦怠感、疲労感などの症状が現れることがあります。妊娠中の体調管理のためにも意識して摂取しましょう。
ビタミンD
ビタミンDには、カルシウムの吸収を促し、骨の形成を助ける働きがあります。日頃から意識的に摂取したい栄養素です。
鉄分とビタミンCの関係と同様に、カルシウムを多く含む食材を摂取する際は、ビタミンDを多く含む食材を一緒に食べると効果的です。ビタミンDは、きのこ類や魚類などに多く含まれています。例えば、チンゲンサイ(カルシウム)ときのこ(ビタミンD)の炒め物などであれば、カルシウムとビタミンDの双方を効率的に摂取できるでしょう。
亜鉛
亜鉛は体内で作用する多くの酵素に含有されており、葉酸を体内に取り込む際の酵素の働きをサポートします。たんぱく質やDNAの合成など、多くの生体反応に関わる栄養素です。
妊娠中の血液や授乳中の母乳に含まれる亜鉛は、妊娠期間や授乳期間が進むにつれて 少なくなることがわかっています。亜鉛不足にならないよう、牛肉や卵アーモンドなど亜鉛を多く含む食材を取り入れましょう。
たんぱく質
たんぱく質は筋肉や臓器など、体を作る材料となる栄養素のため、妊娠中、特に妊娠中期以降は多めに摂取することが大切です。
鶏胸肉などの肉類や鮭などの魚類など食事の中心となる主菜に多く含まれます。また穀類や卵、大豆製品からも摂取できますので、幅広い食品を食べることがポイントです。
食物繊維
妊娠中はホルモンバランスなどの関係で、便秘になりやすい時期です。食物繊維を積極的に摂取して、便秘予防を心がける必要があります。
食物繊維には「水溶性」と「不溶性」の2種類がありますが、水溶性食物繊維は、便を柔らかくする働き、不溶性食物繊維は便の量を増やし、腸の運動をサポートする働きがあります。「水溶性」「不溶性」問わず便通をサポートしてくれるため、母体の健康維持のために食物繊維が豊富な食材を意識して食事に取り入れましょう。
妊娠時期ごとに気をつけたい食事のポイントは?
妊娠の時期によって母体と胎児の状況は変わるため、食事において意識すべきポイントも時期によって変わります。ここでは、妊娠の時期を「妊娠初期(妊娠0~15週)」「妊娠中期(妊娠16~27週)」「妊娠後期(妊娠28~39週)」に分けて、それぞれの時期での食事のポイントについて、詳しく説明します。
妊娠初期 妊娠0~15週
妊娠初期はつわり症状がある方が多い時期なので、十分に食事を取れない場合もあるかもしれません。無理せずつわりが落ち着いたらバランスの取れた食事に整えていくで大丈夫です。
つわりの時は、食べられるものを無理のない範囲で少量にわけて食べましょう。脱水にならないように水分は十分に補給し、思うように食事がとれない場合は、サプリなどを利用するのもよいでしょう。常に何かを食べていないと気持ち悪くなってしまう「食べづわり」がある方は、主食や甘いものだけに偏ると急激な体重増加につながるケースがあるため、こまめに少量ずつ食べるようにすることがすすめられます。
妊娠中期 妊娠16~27週
妊娠中期にはつわりが落ち着いていることが多く、食欲が増しやすい時期です。胎児の成長にはお母さんが摂取した栄養が大きく関わるため、妊娠中に積極的に摂取したい栄養素を中心に、バランスの取れた食事を取ることを心がけましょう。
適正な妊娠中の体重増加はお母さんと赤ちゃんの健康維持・増進につながります。妊娠中の体重増加量が著しく少ない場合、早産や赤ちゃんが小さく産まれるリスクが高まり、逆 に、体重増加が過剰だと巨大児分娩のリスクが高まります。これは赤ちゃんの将来の健康にも影響するといわれています。
また、便秘予防のために食物繊維やヨーグルトなどの乳製品を摂るほか、積極的に鉄分が豊富な食材を取り入れて、貧血予防も意識しましょう。
妊娠後期 妊娠28~39週(h3)
赤ちゃんの成長に伴って必要なエネルギー量が増える時期です。 お腹が大きくなり、胃が圧迫される妊娠後期は、一度に多く食べることが難しい場合もあるでしょう。そのようなときは無理をせず、1回の食事量を減らして食事回数を増やす工夫をして、必要な栄養をしっかり摂りましょう。 この時期は、妊娠高血圧症候群などの合併症が現れる可能性があるため、塩分の摂りすぎには十分注意が必要です。
また赤ちゃんの体を作るたんぱく質をしっかり取り入れましょう。単一の食材からたんぱく質を摂取するのではなく、さまざまな食材からバランスよくたんぱく質を摂取することが大切です。
胎児の栄養はお母さんの食事から
胎児は、お母さんの食べたものから栄養をもらいます。お母さんが栄養不足だったり食べすぎたりすると、胎児にもその影響が及びます。また、胎児にだけ影響が及ぶ食べ物もありますので、そのことを知って食事メニューを考えることが大切です。
不安なことがあればかかりつけの医師に相談しましょう。
この記事は2021年10月6日時点の情報です。
※2025年1月 株式会社RJCリサーチ調べ インターネット調査 調査対象:産婦人科、産科、婦人科、生殖医療関連診療科 150名
Last Updated : 2024/Jul/10 | CH-20240628-09