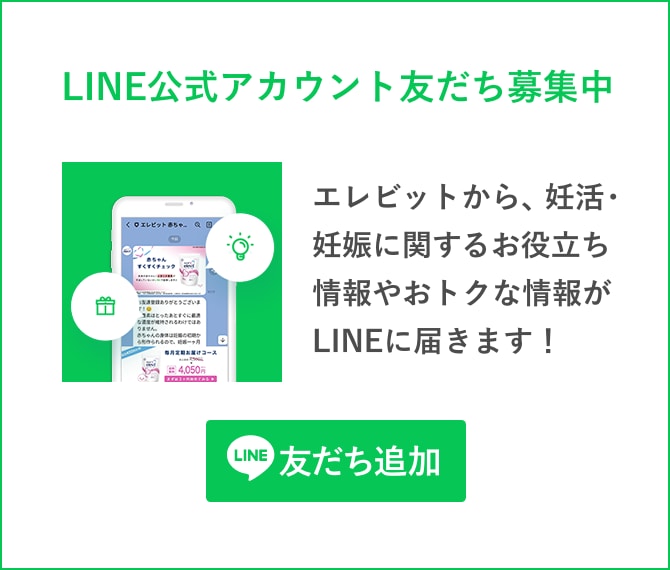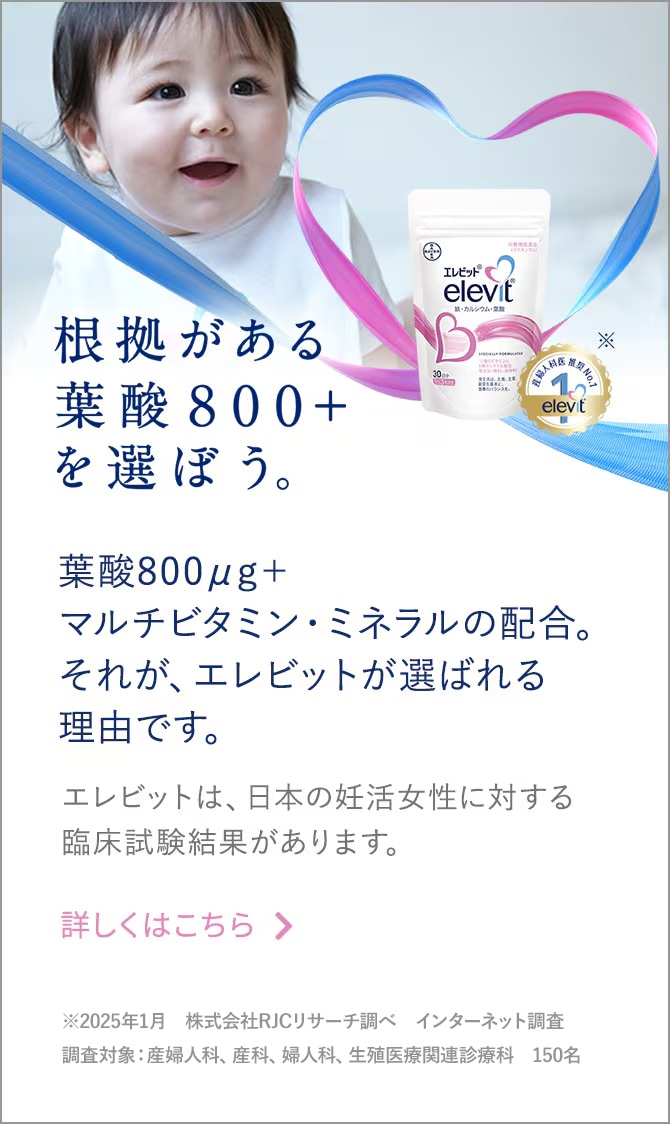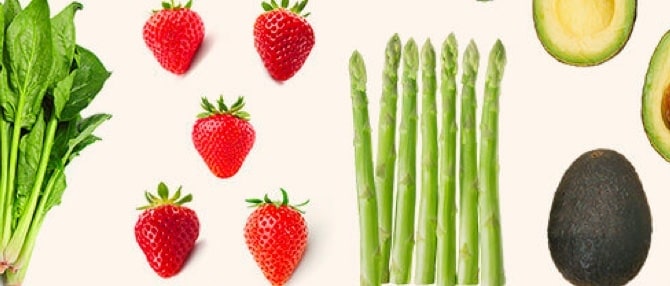トップ>妊活TOP>妊活中に知っておきたいこと>妊活の「悩み」に関するコラム>妊活の期間はどれくらい?実際に取り組んでいるカップルの現状
【医師監修】不妊症とは?検査法や治療法、費用について知りたい
「不妊症」とは、具体的にどんな状態をいうのでしょうか?検査や治療、費用など、疑問に思うことは多くあることでしょう。不妊症にまつわる疑問についてチェックしていきましょう。
1年間避妊をせずに性行為をしても妊娠しない場合は不妊症と定義されます
不妊症は一般的に、避妊をせずに性行為をしても妊娠しない状態が1年間続いた場合と定義されています。
1年様子を見てから産婦人科を受診したほうがいい?
一般的に35歳以上の妊娠は高齢妊娠となるため、30歳以降に妊娠を希望する方にとって、1年は貴重な期間です。そのため、産婦人科への受診を1年待つ必要はなく、妊娠を希望した時点で受診することが勧められます。
現在の子宮や卵巣などからだの状態をチェックしてもらったり、妊活方法や妊娠の確率を高める方法について相談したりすることで、妊娠の確率を高めることに繋がるでしょう。
不妊症の原因はさまざま
女性の不妊症は、排卵がうまくいかない状態(排卵障害)や、卵管の閉塞や癒着、子宮の異常、免疫の異常などが原因となるほか、明らかな原因がわからない場合もあります。
これらの異常を引き起こす原因としては、下記のような疾患が背景となっていることもあります。
- 甲状腺機能異常
- 高プロラクチン血症
- 多嚢胞性卵巣症候群(たのうほうせいらんそうしょうこうぐん)
- 早発卵巣不全(そうはつらんそうふぜん)
- クラミジア感染症
- 子宮筋腫、子宮内膜ポリープ
- 子宮内膜症、子宮腺筋症 など
これらの病気は、適切な治療を行うことで状態の改善が見込めます。早めに発見し、治療することが大切です。
不妊の原因が男性側にあることも少なくありませんので、夫婦で受診することをおすすめします。
不妊症の検査は体の状態にあわせた方法で行います
不妊症の検査には、下記の方法があります。すべての検査を行うわけではなく、診察時に問診が行われ、必要な検査が選択されます。
内診・経腟超音波検査
内診台という椅子のような診察台にのって行われるのが、内診です。内診台にのると、台が動き、背もたれが倒れて、足を開いた状態になっていきます。
その状態で、子宮や卵巣の状態をお腹の上から触診したり、膣のほうから内診したり、膣内に入れるタイプの超音波プローブを使って超音波検査を行ったりします。
子宮卵管造影検査
子宮卵管造影検査は、子宮口から子宮内へ造影剤を注入し、X線によって子宮の形や卵管の閉塞がないかを見る検査です。少し痛みをともなう検査ですが、卵管の通りが良くなるため、検査後に自然に妊娠する場合もあります。
血液検査
血液を採取して、ホルモンの値や血糖値などを調べる検査です。ホルモン検査は、ホルモンの値が月経周期によっても変化しますので、月経中や月経前などに分けて検査が行われます。
その他、より詳細な検査として、腹腔鏡検査・子宮鏡検査、MRI検査などが行われる場合があります。
不妊症には原因にあわせた治療法があります
検査の結果、不妊治療が必要と判断された場合、原因に合わせて下記のような治療法が選択されます。
排卵誘発法
内服薬や注射によって卵巣を刺激し、卵胞の発育や排卵を促す方法です。
内視鏡手術(子宮鏡手術、卵管鏡手術、腹腔鏡下手術)
子宮や卵管を内視鏡で確認し、ポリープや子宮筋腫の切除をしたり、卵管の通りを良くしたりする手術です。
人工授精
精子が少ない、運動率が低いなどの問題がある場合、採取した精液から運動率の高い精子を濃縮し、排卵時期に子宮内に注入する方法です。
体外受精
腟から卵巣に針を刺して採卵し、体外で精子と受精させた後、発育した受精卵を子宮内に返す方法です。
顕微授精
細いガラス針の中に入れたひとつの精子を、採卵した卵子の中に直接注入して受精させる方法です。
不妊治療の保険適用について
2022年4月から不妊治療の保険適用が開始されました。
保険適用の条件をチェックしてみましょう。
| 対象治療法 | 生殖補助医療 (体外受精、顕微授精、採卵、胚培養、胚移植など)、 男性不妊症治療 タイミング法、人工授精 (※一般不妊治療は年齢制限・回数制限はなし) |
| 対象年齢 | 治療開始時の妻の年齢が43歳未満 |
| 保険適用回数 | 40歳未満:1子ごと胚移植6回まで 40歳以上43歳未満:1子ごと胚移植3回まで |
| 婚姻関係の確認 | 下記のいずれかに該当すること 婚姻関係にある事実婚である。事実婚の場合は、下記を確認する ・重婚でない(両者がそれぞれ他人と法律婚でない)こと。 ・同一世帯であること。なお、同一世帯でない場合には、その理由について確認すること。 ・治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。 |
エレビット会員の方ならマイページから、不妊治療保険適用について医師が詳しく解説する動画を見ることができます。
会員登録するとお得でためになる限定コンテンツが満載。ぜひこの機会に会員登録してみませんか?
エレビット会員様限定の3大特典
不妊症は早めの受診が大切
不妊治療は、年齢が若いほど効果があります。そのため、不妊症かもしれないと思ったら、早めに医療機関を受診することが大切です。受診の際は夫婦で受診し、それぞれ必要な検査を受けましょう。原因がわかり治療によって改善できれば、妊娠の可能性は高くなることでしょう。
不妊症や不妊治療について、疑問や不安なことがあれば、受診した際に医師に相談しましょう。
この記事は2022年9月27日時点の情報です。
監修者

神谷 博文先生
医療法人社団神谷レディースクリニック 理事長
1973年、札幌医科大学卒業、同大学麻酔学講座入局。札幌医科大学産婦人科講座、第一病理学講座を経て、斗南病院に勤務。斗南病院産婦人科長として13年間勤務の後、1998年開院。医学博士。麻酔科標榜医、日本臨床細胞学会細胞診専門医。日本産科婦人科学会 産婦人科専門医。
※2025年1月 株式会社RJCリサーチ調べ インターネット調査 調査対象:産婦人科、産科、婦人科、生殖医療関連診療科 150名
Last Updated : 2022/Sep/27 | CH-20220916-22